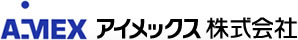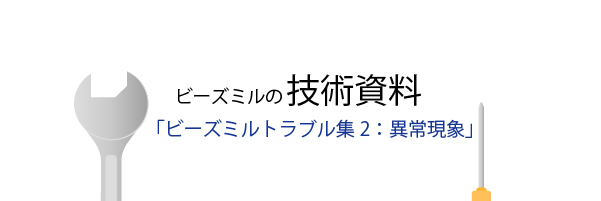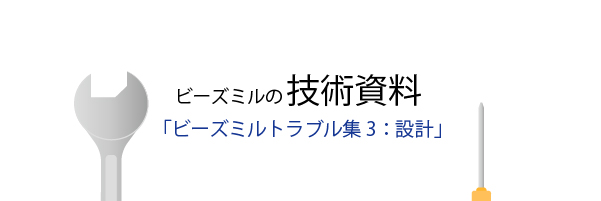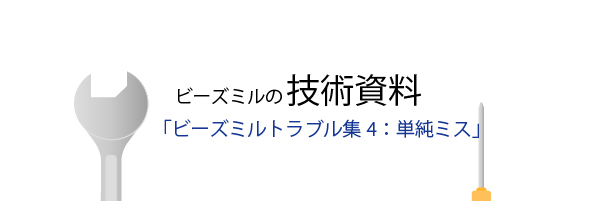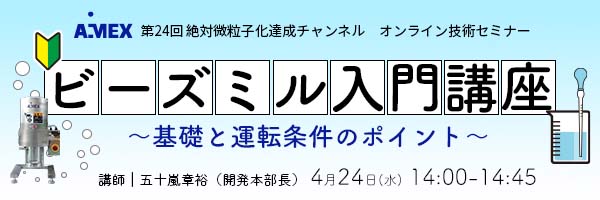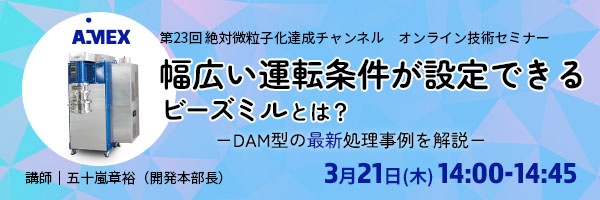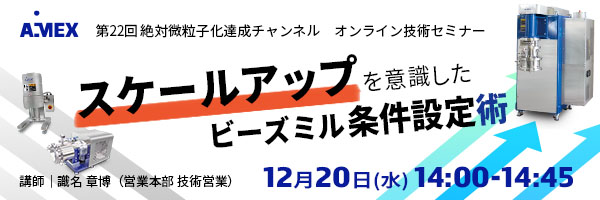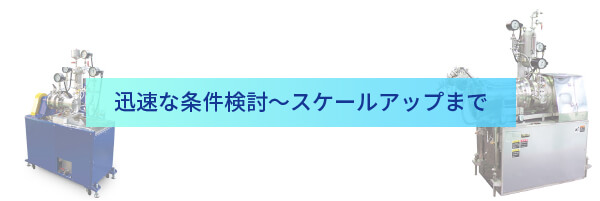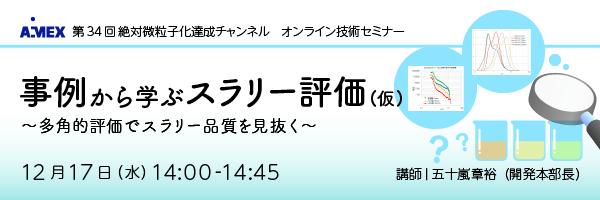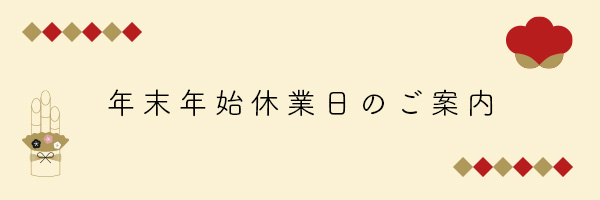ビーズミルトラブル集1:運転操作
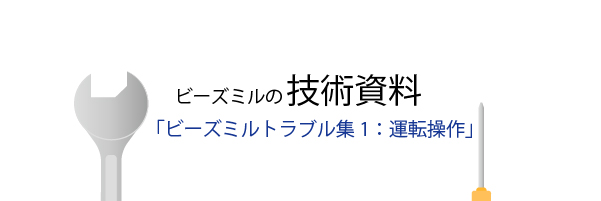
ビーズミルは単純な粉砕機械です。ビーズミル内にビーズが充填されて高速回転で撹拌されているところに、粉体と溶媒の混合物であるスラリーを供給して砕料を超微粒子化しています。 ビーズミルは、砕料に種類やスラリーの固形分濃度の高低などによって、処理物が粉砕室内で微粒子化するとスラリー粘度が急激に上昇し、これに伴って短時間の粉砕室内滞留であるにもかかわらず、処理物の物性が大きく変化します。そして流動状態、伝熱条件、運転動力などに大きな影響を及ぼすと同時に、撹拌機構の高速回転によってビーズや粉砕室部品が摩耗します。 思いがけないトラブルに見舞われることもありますが、単純な機械なため、きちんと対策を取れば非常に効率の良い処理が可能です。今回は、運転操作上のトラブルなどの具体例と対策を述べていきます。
運転操作上のトラブル集
1.テスト機と生産機でフォーミュレーションが違う
機密保持ということで、ユーザーが調合して持参したスラリーを小型テスト機でテストを行いました。
テスト結果から大型生産機にスケールアップしました。1年後に設備が完成して試運転が行われましたが、粒子径が目標に到達しない上に、発熱の制御が出来ず生産運転が大幅に遅れました。
小型テスト機で再テストを行いましたが、当初のデータと大きな違いがありました。機密保持ということから近年はこうしたトラブルが増えています。生産機でフォーミュレーションを変更する時は大変な製品ロスと、無駄な時間を費やす結果となります。フォーミュレーションを変更する場合は、必ず事前に小型のテスト機で条件設定をすることが大切です。
2.テスト機と生産機で処理製品が違う
ビーズミルによる受託加工メーカーが、小型テスト機の結果を基に大型生産機にスケールアップしました。生産機が完成する前に受託加工製品が変更になり、テスト機で実験した試料と異なる製品を生産することになりました。試運転に入りましたが、処理品がテスト時と違うため予定した生産量が大幅に低下しました。
3.ジャケットの汚れ
運転を開始して6ヶ月経過した頃からスラリーの温度が下がらないということで、配管経路の点検、給水温度や給水量などのチェックを行ったが異常がありませんでした。給水源を確認したところ未処理の河水だったことから、粉砕室ベッセルを取り外して点検した結果、冷却ジャケット部に水垢と泥が数mmの厚さで付着していて伝熱効果を阻害していました。
4.担当者交替直後のトラブル
技術・技能の伝承は、世代交代や職場の担当変更などがある時には、きちんと行われなければなりません。しかし、現実には問題が多いです。ビーズミル運転担当者が交代した直後に、トラブルの発生が頻発するケースが多くなります。トラブル原因を究明すると、運転に対する引継ぎが不充分なことが多々あります。
24時間連続運転を行っている生産設備では問題が少ないですが、断続的な運転による生産設備や、実験設備でトラブルが起こっています。これはビーズミルの運転操作は経験と勘による部分が多くあり、個々人のノウハウに係わる領域の引継ぎができないこともあります。
望ましいことは、ビーズミル運転担当者が交代する時期に、ビーズミルメーカーによる定期点検で後任者がメーカーと一緒に点検を行い、運転の立ち上げを経験することです。
5.運転停止中にスラリーが固化
重質炭酸カルシウムの粉砕でサンドグラインダーを使用していましたが、作業の都合でスラリーを抜かずに数時間の運転停止をしました。運転停止中にディスク周囲の重質炭酸カルシウムスラリーが固化しました。そのままの状態で起動したため最下部のディスクが割れました。重質炭酸カルシウムスラリーは固化し易いことから、運転停止前にきちんと洗浄をしないとこうしたトラブルは発生します。 重質炭酸カルシウムに限らず、高固形分濃度のスラリーは運転停止中のスラリー固形化に注意しなければなりません。
6.冷却水がミル内に侵入してスラリーが固化
運転中のミルが突然、安全装置が作動して運転が停止したということから分解点検を行った結果、ジャケットのOリングが老朽化したため微量の冷却水がミル内に侵入していたことが分かりました。処理物は水を嫌い、微量の水でも反応を起こして固化する性能だったことから、処理物の固化によってオーバーロードとなり運転が停止しました。
ビーズミル導入後の点検
以上のようなトラブルを防ぎ、ビーズミルの正常な運転を続けるためには定期点検が大切です。ビーズミル導入後の点検は、ビーズと本体を分けて行うことが望ましいです。
ビーズの種類はガラスビーズ、アルミナビーズ、ジルコンビーズ、ジルコニアビーズ、チタ二アビーズ、窒化ケイ素ビーズなどがあります。しかし、主に使われているビーズはガラスビーズ、ジルコンビーズ、ジルコニアビーズです。耐磨耗はジルコニアビーズ>ジルコンビーズ>ガラスビーズであり、材質によって摩耗の進捗状態の確認時間に違いがあります。ビーズミルの導入から最初のビーズ交換までのビーズ粒径確認は、ガラスビーズ100時間、ジルコンビーズは200時間、ジルコニアビーズは300時間ごとに行うことが望ましいとされています。
ビーズミル本体は日常点検、ビーズ交換時の点検、6,000~7,000時間ごとにメーカーによる開放点検を行うと良いでしょう。
続きはこちら
中山勉:「超微粒子・ナノ粒子をつくる ビーズミル」,工業調査会
■ 次の記事「ビーズミルトラブル集2:異常現象」≫
■ 前の記事「ボールミルとビーズミルのコンタミネーション比較」≫
■ ビーズミル技術資料一覧ページへ ≫